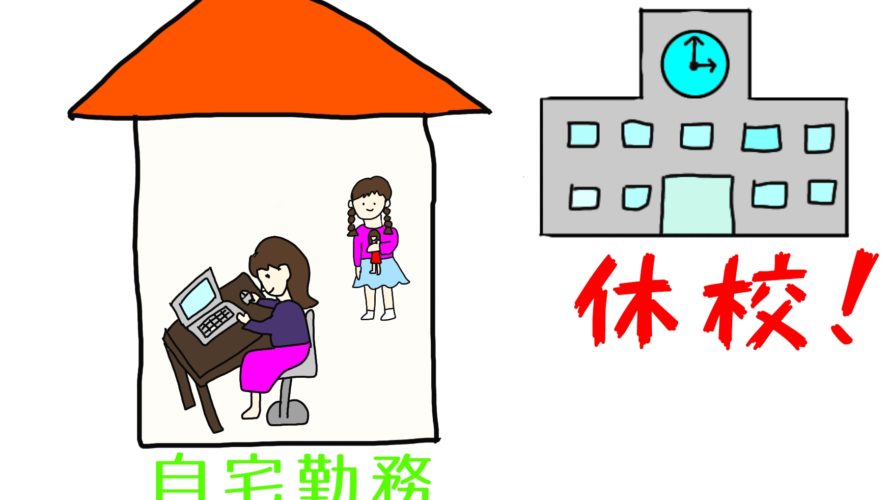【プロジェクト型 就業規則作成】就業規則を別の言い方で表現!3つのポイント
- 2019.08.08
- ニーちゃんのイキイキ日記 働き方がイキイキ 就業規則がイキイキ
- テンプレート, プロジェクト, ユニーク, わかりやすい, わかりやすく, 会議, 作る, 働き方改革, 大阪, 就業規則, 雛形, 面白い

【2019年3月19日公開/2019年8月8日更新】
-1024x644.jpg)
例えば、「労働時間」と書かれるより、「はたらく時間」と書かれた方が読みやすい印象があるニー。
それと同じで「就業規則」って、堅いイメージだニー。
もっと違っていいんじゃない?と思うニー。
今日は、プロジェクトメンバーで、どんなタイトルがよいかを話し合うニー。
就業規則に代わる、どんなタイトルが出てくるか、楽しみだニー。
就業規則のタイトル付けのポイント1「就業規則」は「就業規則」でなくてもよい

労働基準法89条には、「就業規則」という言葉が出てきます。
ですから、一つの事業所で働く従業員数が10名を超えると「就業規則」というタイトルの規則を作らなければならないと思われています。
しかし、「就業規則」の中に書かなければならない内容は決まっていますが、実は「就業規則」という名前にしなくてはならない、ということは定められていません。
もちろん、就業規則と書いても構いませんが、もしその名前の冊子を見たときに「読んでみよう!」と思う方が少ないのであれば、タイトルを変えるのも一つです。
実際に、プロジェクトメンバーのみなさんに「就業規則って読んだことあった?」と聞いた際、「読んだことある」と答えられる方の割合はほんのわずか。
その理由は「自分には関係ないもの」と思っているからではないでしょうか。
特に、プロジェクトを通して作り上げたものであればあるほど、メンバーで話し合った内容を盛り込むワークブックですから、「就業規則」という堅い名前にすることに違和感を感じるかもしれません。
それであれば、「自分たちにも関係ある」「開いてみようかな」と思ってもらえるタイトルにしてみてもよいのではないでしょうか。
◎関連コラム:【プロジェクト型 就業規則作成】チームの価値観を明確にし、共有する
就業規則のタイトル付けのポイント2「自分たちのワクワク感がそこにあるか」

就業規則のタイトルを考える際、これまでの事例を見せることなく「タイトルを考えましょう」とメンバーの皆さんに丸投げしてしまいます。
タイトル決めの意図を語ることはしません。
就業規則ってほんとはこんな意味だったよね、なんてことも語りません。
ただ、目指したい状態だけは共有します。
・このタイトルを見れば「読んでみよう(開けてみよう)」と思うタイトル
・自分たちらしさが表現できると思うタイトル
・何より、自分たちがワクワクできるタイトル
こんな「タイトルを考えてきて下さい」とお伝えします。
すると、「その会社なりの」「その会社の特徴を体現した」タイトルが不思議と生まれてきます。
もちろん、弊社で決めることはできます。
しかしそれだと、どこまでいっても「人が決めたもの」です。
せっかくプロジェクトを通して、自分たちの働き方や待遇、会社のことを考えてきたのですから、そこはメンバーを信じて任せてみましょう。
◎関連コラム:【プロジェクト型 就業規則作成】雛形ではない「オリジナル就業規則」
就業規則のタイトル付けのポイント3「社員と共に作り上げる」と感じる機会に

たくさんのプロジェクトを見てきて、「たかがタイトル、されどタイトル」だと感じています。
私たちは労働法関連の資料をたくさん見ていますが、以前まで国が出している説明資料はこんな内容でした。
「改正●●法について」
それが、最近出された資料では
「年5日の有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」というタイトルが付いていました。
もちろん、実務上必要な方は、どんなタイトルであれ資料を開くことでしょう。
しかし、「どうしても必要というわけではない方」は、「改正●●法」と言われたところでピンとこず、開くことは少ないと思います。
さらに、資料の作成側としても
「改正●●法について」と名付けた冊子より、
タイトルに「わかりやすい解説」というキーワードが入っていた方が
「このタイトルにするのだから、わかりやすいものを作りたい」という意思が働くことでしょう。
これは、就業規則でも言えることです。
「就業規則」と名付けた冊子であれば、国が出しているお堅い雛形が書かれてあっても違和感はありません。
しかし、「私たちの働き方」「プロフェッショナルサービスへの道」「●●(社名)プライド」「トリセツ」などというタイトルがついている冊子であれば、中身ももっと興味を持てる内容になるはずです。
何より、「ちょっと見てみようかな」と思う方が増えるはずです。
それは言い換えれば「自分たちの働き方に興味を持っている人」が増えている証拠です。
たかがタイトル、されどタイトル。
自分たちの目指す姿や大切にする価値観、特徴をあらわすようなタイトルを考えてみてはいかがでしょうか。
「共に作り上げた」という印象につながる、大切な一つの過程です。
◎関連コラム:【プロジェクト型 就業規則作成】ハンドブックを作る3つのメリットと作り方解説
■まとめ
今回は、プロジェクトで作成を進めてきた就業規則の「タイトル決め」について見てきました。
ポイントは次の通りです。
・就業規則というタイトルでなければならないという決まりはない
・タイトル付けのポイントは「自分たちのワクワク感があるか」
・何も言わなくても(意図しなくても)その会社らしいタイトルが出てくる
・興味深いタイトルは、開く人(興味を持つ人)が増えるとともに、内容の精度が高まる効果がある
なお、タイトルは奇抜なものである必要はありません。
また、キャッチフレーズのようなかっこよさも必要はありません。
むしろ「自分たちがどう感じるか」が大切です。
なぜなら「自分たちらしさ」を表すことができ、興味を持つ人が増えればそれで役割は十分果たせるのですから。
会議室を飛び出す、お酒を飲みながら、タバコを吸って雑談しながら、自然の中に行く…
ぜひ、みなさんなりに「自由に発想」してみてくださいね。
■よく読まれているコラム
【就業規則の作り方】リノベーション就業規則で会社の歴史を活かす方法
-
前の記事

【社員合宿研修】「行きたくない」を「行ってよかった」に変える6つの工夫(主催者編) 2019.08.05
-
次の記事

【社員合宿研修は効果あり!?】実施するメリット・デメリット 2019.08.09
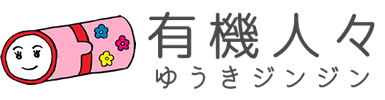



-150x150.jpg)


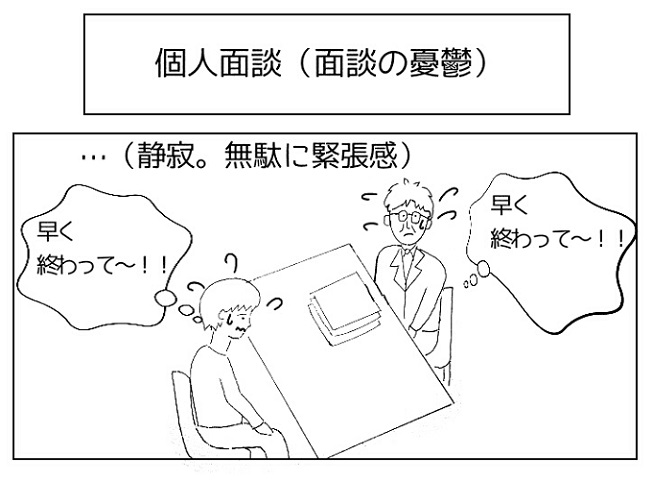


.jpg)